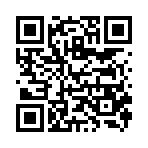2016年03月23日
幼児期の運動遊び 5歳児自由参観
市内のとある園では、数年前から積極的に運動遊びに取り組まれ、卒園を間近に控えた5歳児のこの時期に自由参観を開催されています。
普段では、なかなか見ることができない子どもたちの成長ぶりを保護者の方に見てもらう絶好の機会です。
そんな自由参観に、お誘いを頂いたので、参加させてもらってきました。
さて、ここからがわたしたちが見てきた内容です。
<サーキット遊び>

まず初めに、跳び箱・飛び石・クマさん歩き・鉄棒(前まわり・逆上がり)・カンガルー跳び・かえる跳びの6種類を順にこなすサーキット遊びの様子を見学しました。
スタート位置に並び、先生の「よーい、スタート!!」の声を今か今かと待つ園児たち。
その表情からは「早くしようよ!!」とわくわくしている様子が窺えました。
「よーい、スタート!!」
待ちわびていたように勢いよく飛び出す園児たち。
ぴょんぴょんと順序良く跳び箱や鉄棒などをこなしていきます。
見ていて驚いたのが、全員がすべての種目に喜んで取り組んでいることです。
もう一度言いますが全員です!!
<大縄跳び>
続いては、大縄跳び
二箇所に張られた大縄跳びを跳び越します。
これもサーキットのように全員が順に何周も跳んでいきます。
迫ってくる縄の位置をしっかりと見てタイミングよく縄下に入り・・・ぴょん!

一度は引っかかっても再チャレンジで全員が跳び越すことができました。
これにも大変驚きました。
<ボール体操>
次にひとりひとりがボールを持ち、音楽に合わせてボールを床についたり、真上に投げて落ちてきたところをキャッチしたり、股の間をくくらせたりと自由自在にボールを扱う姿を見せてくれました。

普段の生活や遊びの中だけでは、投げる、捕るといった動作は多くなく、これらの動作を身につけるのは簡単なことではないと思うのですが、おそらく、日課の中に上手く取り入れておられるのでしょう、ここの園児たちは全員が器用にボールを操る姿を見せてくれました。
<得意な遊び>
ボール遊び、こま回し、短縄跳びの中で、ひとりひとりが得意としている遊びを披露してくれました。
自分の保護者を見つけては、目の前まで行って「みてみて~」と得意げに日頃の成果を見せる園児たちの姿はとても輝いていました。
<リズム体操♪>

普段、天気が悪いときに遊戯室で行っているという体操。
どんぐりころころから始まるピアノの伴奏、その変化に合わせて、決まったパターンの動きをして体を動かします。
どんぐりコロコロ (仰向けの状態から片足を上げ、左右にコロコロ転がる)
(仰向けの状態から片足を上げ、左右にコロコロ転がる)
↓
イモリ(ほふく前進のようにお腹をくっつけたまま腕の力だけで前進する)
↓クマ(ハイハイ⇒クマ歩き(お尻を上に上げての四つん這い)⇒馬(立ってギャロップを踏みながら駆ける))
↓
カメ(うつ伏せになり、両足を曲げ、背中を反らした状態を保つように両手で足首を持つ)
↓
ブリッジ
↓
汽車⇒合図でスライディング(腹ばい)⇒また走る(繰り返す)
↓
五色の玉⇒8人1組で円になり音楽に合わせて、おともだちの間をスラロームで一周し、手をつないで回ったり縮んだりする。五色の玉をつないで首飾りにするイメージでの遊び。

ご覧のとおり、動きのレパートリーが多い上に、運動量はなかなかのものです。
これらの活動が終わるころ、園児たちはどこか満足気で、力を出し切った表情も読み取れました。
そして、運動遊びを始めてから、万歩計を園児たちにつけて貰っているそうです。
その平均結果がなんと・・・
○何もしない日・・・3600歩
○登園時の朝一番、全園児で行うランニングや大縄跳びなどの運動(チャレンジ)をした日・・・7500歩
○チャレンジ+運動遊びをした日・・・9100歩
とずいぶん大きな差があります。
大人でもこれだけの歩数を歩くには、かなり意識して歩く必要があると思います。
こうした数値は「目で見てわかる」ので、指標としては大変わかりやすく、参考になります。
数値はとても大切な指標ですが、「できた!」「見てみて」という満足気な子どもたち、知らない間に大きく成長したわが子の姿に感動する保護者の様子を目の当たりにして、ますます幼児期の運動の必要性を感じることができました。
今年度は、勉強会の開催、運動能力調査の協力、そして今回の参観と、少しずつではあるものの、幼児期の運動遊びについての理解を深めることができた一年でした。
また、わたしたちの中で情報共有をすることは大事ですが、それ以上に、ひとりでも多くの一般の人々と共有することが重要だと考えます。
市内のケーブルテレビやスポ推の広報、このブログを通して発信をさせていただきましたが、まだまだ及ばないところです。
そこで、このブログを読んでくださった方にご協力いただきたいと思います。
今晩の晩御飯のとき、明日の勤務先での会話、おとなりさんとの会話・・・だれかとの会話の中で「最近の子どもの体力がね・・・」、「運動遊びって知ってる?」と、是非この話題に触れて、ひとりでも多くの人にこのことを知ってもらえる機会が増えれば、大変嬉しく思います。
最後に、園児たちの発表後、園長先生や担任の先生が仰っていたことを3つ紹介します。
"訓練してきたからできたわけではないんです。毎日、積み重ねてきた結果がこうなったんです。"
"できないことの訓練をするのではなく、挑戦してみたくなるような心の動きを大切にしています。決して無理はしません。誰でもできる内容で、「やってみよう」、「やってみたい」という気持ちを大切に取り組んでいます。"
"決してアスリートの養成ではありません。わたしたちは、跳び箱を8段跳べたり、二重跳びができるようになることを、目指してるのではありません。これから大きくなっていく子どもたちの色々な可能性を広がるように、運動の入り口を大切にし、生涯に亘って運動を楽しみたいと思えるような体づくり、心身ともに健康な生活が送れる人になってほしいと願っての取り組みです。"

普段では、なかなか見ることができない子どもたちの成長ぶりを保護者の方に見てもらう絶好の機会です。
そんな自由参観に、お誘いを頂いたので、参加させてもらってきました。
さて、ここからがわたしたちが見てきた内容です。
<サーキット遊び>

まず初めに、跳び箱・飛び石・クマさん歩き・鉄棒(前まわり・逆上がり)・カンガルー跳び・かえる跳びの6種類を順にこなすサーキット遊びの様子を見学しました。
スタート位置に並び、先生の「よーい、スタート!!」の声を今か今かと待つ園児たち。
その表情からは「早くしようよ!!」とわくわくしている様子が窺えました。
「よーい、スタート!!」
待ちわびていたように勢いよく飛び出す園児たち。
ぴょんぴょんと順序良く跳び箱や鉄棒などをこなしていきます。
見ていて驚いたのが、全員がすべての種目に喜んで取り組んでいることです。
もう一度言いますが全員です!!
<大縄跳び>
続いては、大縄跳び
二箇所に張られた大縄跳びを跳び越します。
これもサーキットのように全員が順に何周も跳んでいきます。
迫ってくる縄の位置をしっかりと見てタイミングよく縄下に入り・・・ぴょん!

一度は引っかかっても再チャレンジで全員が跳び越すことができました。
これにも大変驚きました。
<ボール体操>
次にひとりひとりがボールを持ち、音楽に合わせてボールを床についたり、真上に投げて落ちてきたところをキャッチしたり、股の間をくくらせたりと自由自在にボールを扱う姿を見せてくれました。

普段の生活や遊びの中だけでは、投げる、捕るといった動作は多くなく、これらの動作を身につけるのは簡単なことではないと思うのですが、おそらく、日課の中に上手く取り入れておられるのでしょう、ここの園児たちは全員が器用にボールを操る姿を見せてくれました。
<得意な遊び>
ボール遊び、こま回し、短縄跳びの中で、ひとりひとりが得意としている遊びを披露してくれました。
自分の保護者を見つけては、目の前まで行って「みてみて~」と得意げに日頃の成果を見せる園児たちの姿はとても輝いていました。
<リズム体操♪>

(写真:『どんぐり』の様子)
普段、天気が悪いときに遊戯室で行っているという体操。
どんぐりころころから始まるピアノの伴奏、その変化に合わせて、決まったパターンの動きをして体を動かします。
どんぐりコロコロ
 (仰向けの状態から片足を上げ、左右にコロコロ転がる)
(仰向けの状態から片足を上げ、左右にコロコロ転がる) ↓
イモリ(ほふく前進のようにお腹をくっつけたまま腕の力だけで前進する)
↓クマ(ハイハイ⇒クマ歩き(お尻を上に上げての四つん這い)⇒馬(立ってギャロップを踏みながら駆ける))
↓
カメ(うつ伏せになり、両足を曲げ、背中を反らした状態を保つように両手で足首を持つ)
↓
ブリッジ
↓
汽車⇒合図でスライディング(腹ばい)⇒また走る(繰り返す)
↓
五色の玉⇒8人1組で円になり音楽に合わせて、おともだちの間をスラロームで一周し、手をつないで回ったり縮んだりする。五色の玉をつないで首飾りにするイメージでの遊び。
(写真:『五色の玉』の様子)
ご覧のとおり、動きのレパートリーが多い上に、運動量はなかなかのものです。
これらの活動が終わるころ、園児たちはどこか満足気で、力を出し切った表情も読み取れました。
そして、運動遊びを始めてから、万歩計を園児たちにつけて貰っているそうです。
その平均結果がなんと・・・
○何もしない日・・・3600歩
○登園時の朝一番、全園児で行うランニングや大縄跳びなどの運動(チャレンジ)をした日・・・7500歩
○チャレンジ+運動遊びをした日・・・9100歩
とずいぶん大きな差があります。
大人でもこれだけの歩数を歩くには、かなり意識して歩く必要があると思います。
こうした数値は「目で見てわかる」ので、指標としては大変わかりやすく、参考になります。
数値はとても大切な指標ですが、「できた!」「見てみて」という満足気な子どもたち、知らない間に大きく成長したわが子の姿に感動する保護者の様子を目の当たりにして、ますます幼児期の運動の必要性を感じることができました。
今年度は、勉強会の開催、運動能力調査の協力、そして今回の参観と、少しずつではあるものの、幼児期の運動遊びについての理解を深めることができた一年でした。
また、わたしたちの中で情報共有をすることは大事ですが、それ以上に、ひとりでも多くの一般の人々と共有することが重要だと考えます。
市内のケーブルテレビやスポ推の広報、このブログを通して発信をさせていただきましたが、まだまだ及ばないところです。
そこで、このブログを読んでくださった方にご協力いただきたいと思います。
今晩の晩御飯のとき、明日の勤務先での会話、おとなりさんとの会話・・・だれかとの会話の中で「最近の子どもの体力がね・・・」、「運動遊びって知ってる?」と、是非この話題に触れて、ひとりでも多くの人にこのことを知ってもらえる機会が増えれば、大変嬉しく思います。
最後に、園児たちの発表後、園長先生や担任の先生が仰っていたことを3つ紹介します。
"訓練してきたからできたわけではないんです。毎日、積み重ねてきた結果がこうなったんです。"
"できないことの訓練をするのではなく、挑戦してみたくなるような心の動きを大切にしています。決して無理はしません。誰でもできる内容で、「やってみよう」、「やってみたい」という気持ちを大切に取り組んでいます。"
"決してアスリートの養成ではありません。わたしたちは、跳び箱を8段跳べたり、二重跳びができるようになることを、目指してるのではありません。これから大きくなっていく子どもたちの色々な可能性を広がるように、運動の入り口を大切にし、生涯に亘って運動を楽しみたいと思えるような体づくり、心身ともに健康な生活が送れる人になってほしいと願っての取り組みです。"

(写真:『ブリッジ』の様子)
2015年10月09日
10月7・8日 幼児の体力測定
10月7日(水)、8日(木)は、市内2か所の幼稚園で体力測定のアシスタントに行ってきました。
以前のブログでお伝えしましたとおり、体力測定のお手伝いの希望があった2園でのアシスタントです。
以前のブログ記事↓(ご参考にどうぞ!)
(http://higashioumitaishi.shiga-saku.net/e1190548.html)
内容に入る前に、幼児の体力測定の測定種目をご紹介します。
①25m走
30mの直線路を疾走し、25m地点を通過するまでの時間を測定
②立ち幅跳び
両足同時の踏み切りで、できるだけ遠くへ投げた距離を測定
③ボール投げ
助走しないで利き手の上手投げで投げた距離を測定
④体支持持続時間
両手を伸ばして手を台の上に置き、足を床から離して体重を支えられる時間を測定
⑤両足連続跳び越し
両足を揃えた状態のままで並んだ10個の積み木を順に飛び越す時間を測定
⑥捕球
170cmの高さの紐を越して飛んでくるボールを10球のうち何回キャッチできるかを測定
以上6種目を2日間に分けて測定します。
では、実際にわたしたちが測定した様子をご紹介します。
まず、わたしたちが幼稚園にお邪魔すると・・・
園児達は何が始まるのだろうと興味津々の様子。
「だれ~?」、「今日はなにするの~?」と大歓迎(?)を受け、
あっという間に取り囲まれてしまいました!
それに対して、「何やろね? 走ったり、跳んだりして遊ぼうか!」と答えます。
純粋な園児たちを見ていると「きみたちの体力を測定するのだよ・・・」などとは言えません。。。
そして、本題の測定を順番に進めていきました。
例えば、25m走は、2人ずつ走ってもらっての測定でした。
測定開始前に、“速く走れるようになる準備体操”をみんなで一緒にしました。
「腕をしっかり曲げて!」
「はい、ひざを上にあげて!」
「足をはやく動かしましょう!もっともっと速く!!」
・・・指導員に続いて一生懸命でありながらも、普段したことのないような動きに大はしゃぎで取り組んでくれました。
その結果
・
・
・
5歳の子で速いタイムだと、6秒台前半で評定5段階中の4、5の子もいましたが、中には横のおともだちが気になるのか
真正面を向いて走れず低めの評定になってしまった子もいました。
また、室内種目の『両足飛び越し』でも、タン・タン・タン・・・とリズム良くこなしていく子もいれば、
タン・・・・タン・ガッ!
と積み木を蹴ってしまう、脚を大きく開いてしまうと苦労している子も多くいました。
こうして2日間の測定を終えて・・・
結果が分かるのはしばらく後になるのですが、評定の高い子と低い子の2極化が著しく感じられたので
かなりバラついた結果になるのではないかと予想しています。
今回の測定結果は、今後の取組の参考として、大変重要な意味をもってくると思います。
これからのわたしたちの幼児に対する活動も、一層深く考えていく必要があるのだと再確認することができました。
以前のブログでお伝えしましたとおり、体力測定のお手伝いの希望があった2園でのアシスタントです。
以前のブログ記事↓(ご参考にどうぞ!)
(http://higashioumitaishi.shiga-saku.net/e1190548.html)
内容に入る前に、幼児の体力測定の測定種目をご紹介します。
①25m走
30mの直線路を疾走し、25m地点を通過するまでの時間を測定
②立ち幅跳び
両足同時の踏み切りで、できるだけ遠くへ投げた距離を測定
③ボール投げ
助走しないで利き手の上手投げで投げた距離を測定
④体支持持続時間
両手を伸ばして手を台の上に置き、足を床から離して体重を支えられる時間を測定
⑤両足連続跳び越し
両足を揃えた状態のままで並んだ10個の積み木を順に飛び越す時間を測定
⑥捕球
170cmの高さの紐を越して飛んでくるボールを10球のうち何回キャッチできるかを測定
以上6種目を2日間に分けて測定します。
では、実際にわたしたちが測定した様子をご紹介します。
まず、わたしたちが幼稚園にお邪魔すると・・・
園児達は何が始まるのだろうと興味津々の様子。
「だれ~?」、「今日はなにするの~?」と大歓迎(?)を受け、
あっという間に取り囲まれてしまいました!
それに対して、「何やろね? 走ったり、跳んだりして遊ぼうか!」と答えます。
純粋な園児たちを見ていると「きみたちの体力を測定するのだよ・・・」などとは言えません。。。
そして、本題の測定を順番に進めていきました。
例えば、25m走は、2人ずつ走ってもらっての測定でした。
測定開始前に、“速く走れるようになる準備体操”をみんなで一緒にしました。
「腕をしっかり曲げて!」
「はい、ひざを上にあげて!」
「足をはやく動かしましょう!もっともっと速く!!」
・・・指導員に続いて一生懸命でありながらも、普段したことのないような動きに大はしゃぎで取り組んでくれました。
その結果
・
・
・
5歳の子で速いタイムだと、6秒台前半で評定5段階中の4、5の子もいましたが、中には横のおともだちが気になるのか
真正面を向いて走れず低めの評定になってしまった子もいました。
また、室内種目の『両足飛び越し』でも、タン・タン・タン・・・とリズム良くこなしていく子もいれば、
タン・・・・タン・ガッ!
と積み木を蹴ってしまう、脚を大きく開いてしまうと苦労している子も多くいました。
こうして2日間の測定を終えて・・・
結果が分かるのはしばらく後になるのですが、評定の高い子と低い子の2極化が著しく感じられたので
かなりバラついた結果になるのではないかと予想しています。
今回の測定結果は、今後の取組の参考として、大変重要な意味をもってくると思います。
これからのわたしたちの幼児に対する活動も、一層深く考えていく必要があるのだと再確認することができました。
2015年09月15日
幼児の運動能力向上プロジェクト
東近江市スポーツ推進委員協議会では、これまで青年期、高齢者の体力向上に取り組んできました。
しかし、最近では、幼児期の体力が低いことや積極的に運動をする子どもとそうでない子どもの二極化が顕著と
なってきたと問題視されています。
また、最も子どもの体力が高かった頃(昭和60年頃)の水準を上回ることができるよう、今後5年間で体力向上を維持し、
確実なものにしましょうという“スポーツ基本計画”が文部科学省において策定されました。
そこで、わたしたちも幼児期の運動能力向上に向け、取り組みはじめました。
たとえば、
実際の幼保現場はどうなっているの?
と疑問に思ったので、市内幼稚園の教諭を講師に招き、研修を開催しました。
そこで知った現状・・・
・「椅子にじっと座っていられない」
・「バランスが悪く、すぐ転ぶ、顔から転んでしまう」
・「和式トイレが使えない(しゃがめない)」
えーーーー!?
予想外の現状にわたしたちは驚きを隠せませんでした。
こういった現状から、現場では様々な取組みがなされているということも聞きました。
その一例が“運動遊び”です!!
運動遊び???
運動なのに遊び?
そうなんです、“運動=キツイ”というイメージを持ってしまうことが運動嫌いにしてしまうそもそもの原因
という考えから、
“運動=楽しい”というイメージを持ってもらおうよ!という考え方に繋がり、
遊びの中に運動を取り入れる運動遊びが生まれたのです!!
つまり、運動+遊び=運動遊びなのですね。
そのためにはまず、『運動したくなる環境』が必要です
たとえば園庭の木にロープがぶら下がっていたり、

綱渡りできるような場所があったり・・・

こんな園庭だったら子どもたちは大喜びで自然と遊びますよね!
しかし、環境さえあれば万全ということはなく、運動できるためには
『運動できるからだ』が必要です
たとえば、「かえるとび」や「カンガルージャンプ」など運動するために必要となる基礎能力を育む
プログラムなどがあります。
これももちろん“楽しく”行います!
こうして運動できるからだを手に入れた子どもたちは、目の前の楽しそうな遊具で目いっぱい遊んでいるうちに
自然と体力も向上していくのです
さらに、もうひとつ大切なことがあります
それは・・・
『きっかけ』を与えることです
少しでも上のレベルのことができるようになると嬉しくなって自信もつきます
たとえば、鉄棒にぶら下がることができていた子が前回りができるようになったら・・・
そして逆上がりまでできるようになったら・・・
子どもにとっても周りにとってもこんなに嬉しいことはありませんよね
「ちょっと前回りやってみる?」など周りの大人が『きっかけ』を作ってあげることが大切なのです。
まとめると
運動できる、したくなる環境があり、
運動できるからだ
があると自然に子どもたちは運動好きになる!
そしてそのためには、子どもの発育段階に合わせた無理のない方法で“楽しく”取り組むことが重要なのだということです。
今回の研修を終え、わたしたちも何かできることはないものかと考えました。
・
・
・
ありました!
今年の10月頃から県内、対象幼児施設で幼児の体力測定をすると決定しました。
そして、東近江市内でも9園が実施されるということで、その体力測定のお手伝いができるのではないかと考えたのです。
早速、依頼が舞い込んだので10月7日・8日にお手伝いに行ってきたいと思います!
しかし、最近では、幼児期の体力が低いことや積極的に運動をする子どもとそうでない子どもの二極化が顕著と
なってきたと問題視されています。
また、最も子どもの体力が高かった頃(昭和60年頃)の水準を上回ることができるよう、今後5年間で体力向上を維持し、
確実なものにしましょうという“スポーツ基本計画”が文部科学省において策定されました。
そこで、わたしたちも幼児期の運動能力向上に向け、取り組みはじめました。
たとえば、
実際の幼保現場はどうなっているの?
と疑問に思ったので、市内幼稚園の教諭を講師に招き、研修を開催しました。
そこで知った現状・・・
・「椅子にじっと座っていられない」
・「バランスが悪く、すぐ転ぶ、顔から転んでしまう」
・「和式トイレが使えない(しゃがめない)」
えーーーー!?
予想外の現状にわたしたちは驚きを隠せませんでした。
こういった現状から、現場では様々な取組みがなされているということも聞きました。
その一例が“運動遊び”です!!
運動遊び???
運動なのに遊び?
そうなんです、“運動=キツイ”というイメージを持ってしまうことが運動嫌いにしてしまうそもそもの原因
という考えから、
“運動=楽しい”というイメージを持ってもらおうよ!という考え方に繋がり、
遊びの中に運動を取り入れる運動遊びが生まれたのです!!
つまり、運動+遊び=運動遊びなのですね。
そのためにはまず、『運動したくなる環境』が必要です
たとえば園庭の木にロープがぶら下がっていたり、

綱渡りできるような場所があったり・・・

こんな園庭だったら子どもたちは大喜びで自然と遊びますよね!
しかし、環境さえあれば万全ということはなく、運動できるためには
『運動できるからだ』が必要です
たとえば、「かえるとび」や「カンガルージャンプ」など運動するために必要となる基礎能力を育む
プログラムなどがあります。
これももちろん“楽しく”行います!
こうして運動できるからだを手に入れた子どもたちは、目の前の楽しそうな遊具で目いっぱい遊んでいるうちに
自然と体力も向上していくのです
さらに、もうひとつ大切なことがあります
それは・・・
『きっかけ』を与えることです
少しでも上のレベルのことができるようになると嬉しくなって自信もつきます
たとえば、鉄棒にぶら下がることができていた子が前回りができるようになったら・・・
そして逆上がりまでできるようになったら・・・
子どもにとっても周りにとってもこんなに嬉しいことはありませんよね
「ちょっと前回りやってみる?」など周りの大人が『きっかけ』を作ってあげることが大切なのです。
まとめると
運動できる、したくなる環境があり、
運動できるからだ
があると自然に子どもたちは運動好きになる!
そしてそのためには、子どもの発育段階に合わせた無理のない方法で“楽しく”取り組むことが重要なのだということです。
今回の研修を終え、わたしたちも何かできることはないものかと考えました。
・
・
・
ありました!
今年の10月頃から県内、対象幼児施設で幼児の体力測定をすると決定しました。
そして、東近江市内でも9園が実施されるということで、その体力測定のお手伝いができるのではないかと考えたのです。
早速、依頼が舞い込んだので10月7日・8日にお手伝いに行ってきたいと思います!